生理は女性にとって健康状態のバロメーターでもあります。
生理の基礎知識や、生理中でも快適に過ごすためのセルフケアをご紹介。
排卵期出血とは?排卵期の症状や過ごし方・対策を医師が解説

「生理はまだなのにおりものに血が混ざっている」「毎月生理と生理の間で2~3日ほど出血がある」といった経験をしたことはありませんか?自然な生理は25日~38日周期で訪れるため、タイミングのずれに驚いてしまいますよね。実際の生理予定日よりも2週間前後早く来る出血は、「排卵期出血」である可能性が高いです。
今回は、排卵期出血について詳しく紹介していきます。出血の特徴や対策方法、また不正出血が起こる病気などを解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
もくじ
排卵期出血とは?
まず排卵期出血とは、次の生理開始日から2週間前の排卵期に起こる出血のことです。1か月の女性ホルモンの動きを分けると、下記の4つの期間に分類できます。
- ・生理中
- ・卵胞期
- ・排卵期
- ・黄体期
排卵期の期間に、エストロゲンの分泌量が大きく変化します。この影響で子宮内膜の一部が剥がれ落ちて、出血が起こることがあります。
また、排卵期出血は必ず全ての人に起こる症状ではありません。出血量が少なく、1~3日で終わる場合は心配しすぎる必要はありません。しかし、出血量が多い場合や、1週間以上続く、痛みが強いなどの症状がある場合は医療機関を受診しましょう。
排卵期出血とは?妊娠は関連性がある?
排卵期出血と妊娠に関連性はない
結論からいうと”排卵期出血と妊娠に直接的な関連はありません”。
排卵時期に増えたエストロゲンは排卵後に一時的に減り、プロゲステロンが増加します。
エストロゲンは子宮内膜を厚くさせ、プロゲステロンは、厚い子宮内膜中の分泌腺を増やし妊娠をしやすくする状態を作る働きがあります。排卵期には子宮内膜に影響を与えるホルモンの大きな変化により子宮内膜が剥れて性器出血を起こします。これが”排卵期出血”です。
排卵期出血はホルモンのダイナミックな変化によって起こるものなので、妊娠とは直接的な関連性は無いといえます。
実際に排卵しているかは、基礎体温で確認可能
正常な排卵が起きている場合は、「低温期」と「高温期」に分けられます。
それぞれ約14日間ずつで、一定のサイクルで繰り返されるようになっています。
低温期は生理1日目~排卵前にあたる時期(約2週間)なので、排卵が起きれば、排卵日から次の生理までは高温期(約2週間)になります。
もし体温が上がらずに低温期が続いてたら排卵が起きていない可能性があるので注意しましょう。
基礎体温を毎日測る習慣をつけることで排卵しているかどうかを確認することができます。
つけ始めは綺麗に低温期と高温期に分かれていないと不安になる方もいるかもしれませんが、実際には測るときの体調や測り方などで微妙な変化が生じるので神経質になりすぎないで大丈夫ですよ。
排卵期出血の特徴
排卵期出血の量や色、出血が続く期間について解説します。まず出血の量は少量であることが多く、おりものくらいの量や下着に少し付く程度の量であることが多いです。おりものシートを使用すれば問題ないくらいの量といえるでしょう。出血の色については、排卵期出血はおりものに混じることが多いため、ピンクや赤、茶色など個人差があります。
また出血は1~3日で治まることがほとんどです。生理のように1週間も続かないといわれています。
排卵期の体調不良を緩和させる対策
生理期間に加え排卵時期にも起こる体調不良に、憂鬱になる女性も多いでしょう。しかし、生理周期に合わせた体調管理はとても大切です。排卵期は以下の3点を心がけて過ごしてみませんか?
体を温め、血行を良くする
靴下や手袋などで末端の冷えを防ぎ、とくに腹部はカイロや腹巻などで温かく保つように心がけましょう。身体を締め付ける下着は血行を悪くするので、リラックスできるものを選んでみましょう。入浴はややぬるめのお湯に足を伸ばしてゆったりと浸かることで、心身ともにポカポカになります。心も体もリラックスできるとより良いでしょう。
生活リズムを整える
ホルモンは体内時計に合わせて分泌されます。そのため、メリハリのある生活を目指し、早寝早起きで生活リズムを整えましょう。適度な運動はもちろん、栄養バランスの良い食事を1日3食しっかりととることも大切です。
ストレスをためこまない
精神的・身体的ストレスは自律神経のバランスを崩し、ホルモンの分泌を低下させます。ストレスを感じている状態が続くと交感神経が優位になるため様々な不調をきたします。手軽にストレス発散をする方法を身につけてみましょう。10分くらいでいいので腹式呼吸でリラックスする、好きな音楽を聴いてみるなど、自分なりの工夫をしてみてはいかがでしょうか。リラックスすると副交感神経が優位になるので、全身の血流もよくなりますよ。
排卵期出血と不正出血の見分け方とは
不正出血は生理ではない時期に性器出血があることを指します。
そのため、先ほど説明した排卵期出血も不正出血のひとつです。
おりものや下腹部痛が生じることもありますが、基本的には問題はないといえます。
ただし、出血量が多かったり痛みが強い場合、出血の期間が長い場合(2週間以上)は子宮内膜ポリープや子宮頸がんなどの病気が隠れている可能性があるので、その際には病院の受診も検討しましょう。
不正出血の場合に注意したい病気
排卵期出血は一時的な出血ですが、なかには病気が原因となって発生している不正出血の可能性もあります。では、具体的に不正出血にはどのような病気が隠れているのでしょうか。
膣炎
膣炎は膣の粘膜に生じる感染性、非感染性の炎症のことをいいます。感染による膣炎は、大腸菌やトリコモナス、カンジダ、淋菌、クラミジアなどの病原体に感染することで起こります。性感染症と思われることもありますが、必ずしもそうとは限りません。下着や衣類の締め付けが強かったり、ナプキンやタンポンを長時間替えなかったりすることでも発症することもあります。また閉経後には、女性ホルモンのエストロゲン分泌の低下が原因となり発症する萎縮性膣炎も考えられます。
膣炎では、膣内に炎症が起こることから不正出血が起きます。他にはおりものが黄色くなる、おりものがボロボロとした形状になる、性器周辺の強いかゆみ、排尿時の痛み、残尿感などの症状がみられます。完治させないと再発しやすく、パートナーと性行為をしたときは一緒に治療を行う必要がある場合もあります。
無排卵出血
無排卵出血とは、生理のような出血はあるものの、ホルモンバランスの乱れや何らかの病気が原因となり、生理周期のなかで1回あるはずの排卵がない状態のことです。不妊の原因になることがあるため、早めの対処が必要です。
排卵がされていない状態でも、エストロゲンの分泌は行われているため、少しずつ子宮内膜は厚くなっていきます。一定の厚さ以上になると維持できなくなり、生理のような出血が起こるのです。無排卵出血を長期間そのままにしておくと、不妊だけでなく子宮体がんを引き起こす原因になったりすることもあります。
子宮頸がん
子宮頸がんは子宮の下の部分である管状の子宮頸管や子宮の入口に発症するがんです。HPV(ヒトパピローマウィルス)に感染することで起こります。HPVは性交渉をしたことがある女性の半数以上が感染することがあるといわれています。90%の人は感染しても2年以内に自然に排出されていきますが、10%の人はHPV感染の状態が続きます。
そのまま自然排出されなかった人の一部は、異形成というがんの前段階の病態を経て、年数をかけて子宮頸がんに進行していきます。初期のうちは自覚症状がほぼありません。不正出血・性交時の出血・下腹部の痛み・水っぽいおりものや粘液が多く出るなど、症状が出る頃にはがんが進行しています。20代〜30代の方に発症が多いことがわかっており、ワクチンの接種や1~2年に1回の定期検診で予防、早期発見・治療が可能です。
子宮体がん
子宮体がんは、子宮の中でも子宮頸部の上の方にある子宮体部に起こるがんです。エストロゲンが子宮内膜に影響することで発生するため、子宮内膜がんとも呼ばれています。肥満である、欧米型の食生活が多い、出産をしたことがない、といった方は、エストロゲンの影響が大きく、危険因子となります。
子宮体癌は、子宮内膜増殖症という前段階を経て進行していくことが知られています。その他にも、がんの関連遺伝子の異常によって発症することもあり、比較的高齢者に多くみられます。また高血圧、糖尿病、近親者に乳がん・大腸がんを患った方がいる場合にも発症リスクが高まるため、定期的な検診が望ましいです。
ポリープ
ポリープは粘膜にできるふくらみのことです。子宮頸管ポリープと子宮内膜ポリープの2つがあります。一言でポリープといっても、検査や診察を進めるとがんや筋腫だったということがあるため、注意が必要です。子宮頸管ポリープは30~40代の女性に多くみられ、ほとんどが良性ですが、大きいものや不正出血を多くするものの場合はがんの可能性があるため摘出します。子宮から筋腫が伸びてきているものがポリープのように見えることがありますので、そのときは手術で取り除きます。
子宮内膜ポリープは子宮頸管よりも奥にできるポリープのことです。症状は不正出血や過多月経などがみられます。ポリープの大きさや数、出血の程度はさまざまですが、なかには貧血や不妊につながる場合もあるといわれています。
子宮筋腫
子宮筋腫は、30歳以上の女性のうち、20%〜30%が発症しているといわれています。子宮の平滑筋にできる良性の腫瘍なため、悪性腫瘍のように命に係わる疾患ではありませんが、貧血や痛みなど様々な症状の原因となります。発生する部位によって子宮の内側(粘膜下筋腫)、子宮の筋肉の中(筋層内筋腫)、子宮の外側(漿膜下筋腫)の3つに分類されます。
不正出血は粘膜下筋腫で起こることがあります。また、水っぽいおりものが増えることがあります。症状は過多月経、月経期間が長くなる過長月経、生理痛などが挙げられます。筋腫の大きさによっては他の臓器に影響することもあり、腰痛や頻尿、便秘などを起こすこともあります。
排卵期出血で受診した方がいいケース
排卵期出血は排卵にともなって起こるため、少量の出血が1~3日続く程度であれば心配しすぎる必要はありません。しかし、なかには前述のとおり子宮がんなど思わぬ病気が原因となっている可能性があります。病院を受診する目安として、「出血量が多い」「下腹部などの痛みが強い」「不正出血を繰り返す」「不正出血が2週間以上続く」このような症状に心当たりがある場合は早めに病院を受診しましょう。早期に受診することで出血を止めることにもつながります。
排卵期出血はピルで改善
出血が病気によるものではない場合であれば、ピルによって生理をコントロールすることも有効的です。ピルを内服することによって、ホルモンバランスを一定に整え、生理周期を安定させることができます。ピルを服用することで排卵を抑えられるので、排卵期出血を改善することにも繋がります。ピルを上手に活用して、ストレスフリーな生活を目指したいですね。
ピルについては、下記の記事で詳しく説明しているので、あわせてチェックしてみてください。
ピルをはじめるならメデリピル
前述の通り、排卵期出血には低用量ピルの服用で排卵を抑えて改善できる可能性があります。
ピルの服用経験がなく、ピルを飲んでみたいけど、安心して信頼できる方法で始めたいという方に、オンラインピル診療・処方サービスのメデリピルがおすすめです。
メデリピルでは、現役の産婦人科医が診療から処方までをオンライン上で行い、自宅にピルが届くので、オンラインでも安心してピルを始めることができます。
メデリピルでは、ご自身に合ったピルを医師と相談しながら決めることができ、サービス利用期間中であれば診療代はずっと無料なので、服用中の不安なことや悩みを、いつでも医師に相談することができるサポート体制が整っています。
また、低用量ピル定期便 ※1 の場合、初月ピル代0円 ※2 で始めることができます。まずは試してみたい!という方におすすめです。
※1 3シート目受け取りまで解約不可
※2 別途送料550円

メデリピルは、いつでもスマホから簡単に受診できる、「誠実」と「続けやすい」を大事にしたオンラインピル診療サービスです。初月ピル代無料、診療代はずっと無料。国内最安クラスで提供しています。
※医師の診療時に処方された場合、最低3シートは服用いただいた上でご自身に合っているか判断していただきたいため、3シート目受け取りまでは解約は不可となります
メデリピルについて詳しく知る
→低用量ピルの料金について詳しくはこちら
メデリピルの5つのこだわり

1ヶ月無料のお試し期間
ピル初心者の方でも安心して服用いただけるよう、低用量ピルは初月無料でお届けします。
※医師の診療時に処方された場合、最低3シートは服用いただいた上でご自身に合っているか判断していただきたいため、3シート目受け取りまでは解約は不可となります
診療担当するのは現役の産婦人科医
専門的な知識を持った現役産婦人科医が診療を担当をするので、生理やカラダに関する不安や疑問を安心して相談することができます。
何度でも診療・再診無料
服用中の体調や副作用など、産婦人科の専門医にいつでも気軽にご相談ください。
予約から診療までLINEで簡単
診療予約や、予約日・配送日やプラン変更など、LINE一つで行うことができます。
正しい知識をお届け
ピルや女性のカラダに関する知識を定期的にお届けしています。
※メデリピルは医療機関とユーザーを繋ぐプラットフォームです
※診療やピルの処方等は保険適用外・自由診療であり、医療機関に所属する医師が行います
まとめ
今回の記事では、排卵期出血とはどのようなものか、また不正出血を起こす病気について紹介しました。生理ではない時に起こる出血は、不安な気持ちになりますよね。日常的にピルを服用しておくことで、ホルモンバランスを一定に保つことができるので、選択肢の一つとして考えてみるのも良いでしょう。ピルを服用していたとしても、子宮や卵巣の病気は自覚症状を感じづらいこともあるので、定期的に検診を受けることが大切です。
監修者

カテゴリ一覧
 漫画
漫画
こんな経験”あるある!”と思わず頷いてしまう?mederiユーザーからの体験談に基づいた、mederiオリジナル漫画シリーズです。生理やピル・女性の健康に関して、楽しく学んでみましょう!









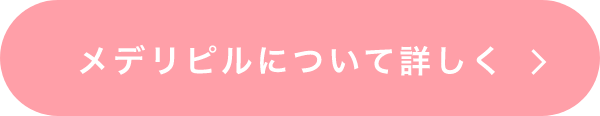

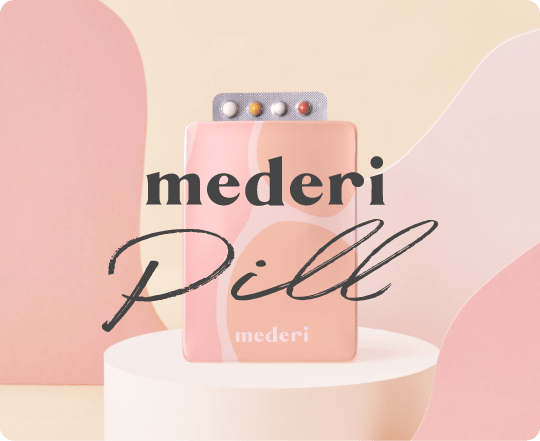






 予約に進む
予約に進む

