生理は女性にとって健康状態のバロメーターでもあります。
生理の基礎知識や、生理中でも快適に過ごすためのセルフケアをご紹介。
生理前の高温期とは?基礎体温の仕組みや予測する方法を解説

生理前になると、なんとなく熱っぽく、体温が上がるのを感じたことはありませんか?それは高温期と呼ばれます。この記事では、基礎体温とその仕組みについて解説します。身体の仕組みや、今後の妊娠に向けて必要な知識を学んでいきましょう。
もくじ
そもそも基礎体温とは?
基礎体温とは、身体的、精神的に安静状態にあるときの体温のことです。一般的には、女性が朝起きる前に、横になった状態で舌下で計測する体温のことをいいます。また、この基礎体温はホルモンの分泌によって変化が起こります。排卵が正常に行われている健康な女性の基礎体温は、低温期と高温期の二相になり、それが一定のサイクルで繰り返されます。
高温期とは
高温期とは、排卵後から生理前までの体温が上昇しているときのことです。人によっては生理前にぼーっと熱っぽさを感じることもあります。
基礎体温の周期と生理前の体温上昇の仕組み

上記のグラフは、生理周期と基礎体温の変化を表しています。
女性の基礎体温は低温期と高温期に分かれており、生理が終わって、おおよそ12〜14日目で排卵後に体温が上昇する高温期に入ります。
一般的に高温期では個人差はあるものの、37℃近くまで体温が上がるという方もいます。
微熱があるように感じることもありますが、これは高温期の症状のひとつといえます。
高温期は生理周期でいうと「黄体期」と呼ばれる時期で、その名の通り「黄体ホルモン」のプロゲステロンが多く分泌されます。プロゲステロンの働きによって体温が上昇するため、ほてりを感じたり微熱があるように感じるのです。
黄体期を過ぎると生理が始まるため同時に体温が下がります。女性の身体は、これらの体温変化を生理周期に伴い繰り返していくのです。
高温期の体温はどのくらい上がるのか
体温には個人差がありますが、0.3度から0.5度まで上がるのが一般的です。実際には、高温期の体温は36.7~36.9度となり、37度近くまでに高くなるケースも多いです。体温を上げる黄体ホルモンの影響や、排卵後の急激なホルモンバランスの変化によって、身体には冷えやむくみが起こります。また精神的にはイライラや怒りっぽくなる、不安感が増したり、眠気が強くなったりなどの症状もみられます。つまり黄体期は、体も心も万全な時期とはいえないでしょう。また、この黄体期の後半に起こる月経前症候群(PMS)の症状に悩む人も多いです。
高温期に対応するには、基礎体温の計測が重要
高温期は生理前であり、高体温のほかにも不調が多い時期です。毎日基礎体温を計測することで、自分の体の状態を把握しておくといいでしょう。加えて、妊娠を希望する場合は、基礎体温を計測することで、まず自分の排卵の時期をきちんと把握しておくことが重要です。しかし、1周期のみでは平均的な体調判断ができないため意味がありません。まずは続けてみることから始めてみましょう。
基礎体温の正しい測り方
基礎体温は、婦人体温計で測りましょう。婦人体温計は、体温の微妙な変化を確認することができます。測り方のポイントは以下の通りです。
①安静状態で測る
起床したら、体を動かさずに、寝たままの状態で検温しましょう
②舌下で、口を閉じたままで測る
計測中は口で息をしないようにしましょうできるだけ決まった時間に計測することも大切です
継続的に基礎体温を記録して体調管理に役立てましょう。
基礎体温は記録をしておこう
基礎体温は、グラフが描きやすいノートや、アプリに記録しましょう。データをみられる状態にしておくことで、今の体の状態を把握することが可能です。病院を受診する際にも役に立ちます。加えて、薬を飲んだ、二日酔いである、など体調に関わる必要な情報もメモしておきましょう。
病院の受診が必要な高温期の症状は?
実際の基礎体温は、その日の体調や室温、測り方などの微妙なことで、誤差が出てしまうものです。しかし、以下の場合には病院に受診する必要があります。
・高温期が短い場合
正常な場合は、約10日以上続きます。それより短期間の場合に考えられる疾患は、黄体機能不全です。
・高温期が長い場合
高温期が14日以上続く場合は、妊娠の可能性が考えられます。
・グラフが2相に分かれていない(無排卵周期)
無排卵月経が疑われます。排卵がないため、体温の変化が起こらない状態です。
グラフの線がバラバラの場合
不規則な生活、体温計の故障、などさまざまな原因が考えれます。しかし、病気の可能性もあるため早めに受診しましょう。
生理前でだるさを感じるときは
生理前になると体温の上昇だけでなく、人によっては身体が重く感じたり、倦怠感のようなだるさを感じることもあります。
このような症状が出る原因は明確にはわかっていませんが、生理周期に伴う女性ホルモンのバランスが変化することによって、気分をコントロールする役割を持つセロトニンやγアミノ酪酸に影響を及ぼしている可能性があるとされている説が有力です。
また、生理前の急激な血糖値の上昇やビタミン、カルシウム不足が原因となっている場合もあります。普段から生活習慣を整えておきましょう。
また、低用量ピルや超低用量ピル、漢方薬も効果が期待できます。特に、低用量ピルは生活改善薬とも呼ばれており、継続的な服用でホルモンバランスを整えて生理前後の負担を改善できることが期待できます。
ピルをはじめるならメデリピル
ピルの服用経験がなく、ピルを飲んでみたいけど、安心して信頼できる方法で始めたいという方に、オンラインピル診療・処方サービスのメデリピルがおすすめです。
メデリピルでは、現役の産婦人科医が診療から処方までをオンライン上で行い、自宅にピルが届くので、オンラインでも安心してピルを始めることができます。
メデリピルでは、ご自身に合ったピルを医師と相談しながら決めることができ、サービス利用期間中であれば診療代はずっと無料なので、服用中の不安なことや悩みを、いつでも医師に相談することができるサポート体制が整っています。
また、低用量ピル定期便 ※1 の場合、初月ピル代0円 ※2 で始めることができます。まずは試してみたい!という方におすすめです。
※1 3シート目受け取りまで解約不可
※2 別途送料550円

メデリピルは、いつでもスマホから簡単に受診できる、「誠実」と「続けやすい」を大事にしたオンラインピル診療サービスです。初月ピル代無料、診療代はずっと無料。国内最安クラスで提供しています。
※医師の診療時に処方された場合、最低3シートは服用いただいた上でご自身に合っているか判断していただきたいため、3シート目受け取りまでは解約は不可となります
メデリピルについて詳しく知る
→低用量ピルの料金について詳しくはこちら
メデリピルの5つのこだわり

1ヶ月無料のお試し期間
ピル初心者の方でも安心して服用いただけるよう、低用量ピルは初月無料でお届けします。
※医師の診療時に処方された場合、最低3シートは服用いただいた上でご自身に合っているか判断していただきたいため、3シート目受け取りまでは解約は不可となります
診療担当するのは現役の産婦人科医
専門的な知識を持った現役産婦人科医が診療を担当をするので、生理やカラダに関する不安や疑問を安心して相談することができます。
何度でも診療・再診無料
服用中の体調や副作用など、産婦人科の専門医にいつでも気軽にご相談ください。
予約から診療までLINEで簡単
診療予約や、予約日・配送日やプラン変更など、LINE一つで行うことができます。
正しい知識をお届け
ピルや女性のカラダに関する知識を定期的にお届けしています。
※メデリピルは医療機関とユーザーを繋ぐプラットフォームです
※診療やピルの処方等は保険適用外・自由診療であり、医療機関に所属する医師が行います
まとめ
この記事では、基礎体温とその仕組みについて解説してきました。低温期と高温期の違いや、その理由について理解することはできたでしょうか。自分の体の状態を理解するとともに、ライフプランを考える上での参考にしてみてください。
監修者

カテゴリ一覧
 漫画
漫画
こんな経験”あるある!”と思わず頷いてしまう?mederiユーザーからの体験談に基づいた、mederiオリジナル漫画シリーズです。生理やピル・女性の健康に関して、楽しく学んでみましょう!








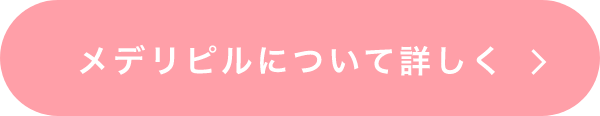

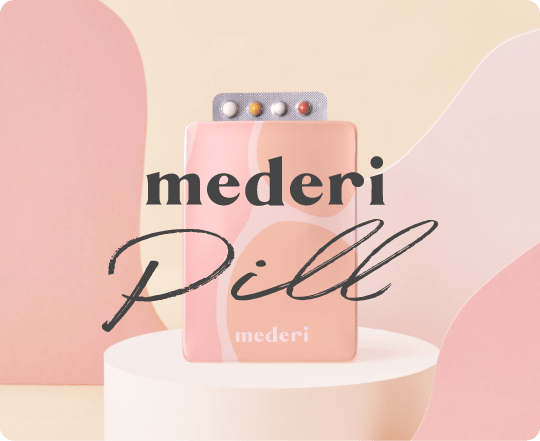







 予約に進む
予約に進む

