生理は女性にとって健康状態のバロメーターでもあります。
生理の基礎知識や、生理中でも快適に過ごすためのセルフケアをご紹介。
【医師監修】着床出血はいつ起きる?生理の違いは?症状や確認方法を解説

妊娠を望んでいる方にとって、着床出血の有無は気になるところですよね。また避妊を希望している方にとって、いつもと違うタイミングで出血が起こると「着床出血かも?」と不安に思うこともあるでしょう。
今回は着床のサインについて、そもそも着床とは何か、着床した場合にはどのような症状がいつ頃現れるか、その後どうすれば良いかなどについてを詳しく解説します。
もくじ
そもそも着床とは?いつ起きる?
着床とは、性行為後に精子と卵子が受精してできた受精卵が細胞分裂を繰り返しながら1週間〜10日位の期間をかけて胚となり子宮に辿り着き、子宮内膜にもぐりこむことを指します。着床することで、妊娠が成立します。
着床完了のサイン
全員に必ず見られる着床完了のサインというものはありません。着床が起こる頃に、感じることがある症状はいくつかあります。たとえば、おりものの量や色が変わった、頭痛がある、お腹が張る、吐き気がする、熱っぽく感じる、眠気を感じるなどの症状です。
無症状だからといって着床していないと言い切ることもできません。着床完了時に見られるサインとして最も多いものは、出血やおりものの変化、下腹部痛などです。
着床完了のサインが出るタイミング
着床完了のサインは、妊娠3週~4週の時期に現れます。「性行為の日から考えると、3週間も経っていないのでは?」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、これは妊娠週数の数え方と関係があります。
妊娠週数を数えるときには、受精(性行為後)から数えるのではなく、最終月経の開始日を「妊娠0週0日」として数えます。月経開始から数えて2週間ほどで排卵が起こりますので、受精した時点ですでに妊娠2週となっています。そこから1週間ほどで着床が起こりますので、着床時点では妊娠3週ということになるのです。
着床の時期にみられる主な症状
受精だけでなく、着床時期の女性の体にもさまざまな変化が起こります。ここでは、着床の時期にみられる特徴的な体の変化を解説します。
おりものの変化
おりものは、ホルモンの影響で量や性状が変わります。受精が完了すると妊娠維持のために、女性ホルモンであるエストロゲンが分泌され、おりものの量が増えやすくなります。おりものの色は半透明から乳白色や薄茶色に変化し、いつもよりも水っぽくサラサラとした状態へと変化します。
着床出血
着床出血とは、妊娠初期に起こる出血のことです。受精卵が着床する際に子宮内膜を傷つけてしまい、出血としてあらわれることを指します。これは受精卵が子宮内膜に定着するための出血であり、胎盤を形成するための工程です。着床前後の1〜2日にかけて少量の出血があれば、着床出血を疑います。
出血があるとびっくりしたり、心配になったりする方も多いですが、決して異常な出血ではありません。着床出血は着床のあとに起きやすい症状の1つともいわれていますが、必ずしも全員に起こるわけではありません。
着床出血がないからといって「着床していない」ということではありません。他の兆候も見逃さないようにしましょう。
また、妊娠超初期症状については下記の記事で、もっと詳しく説明しているので、あわせてチェックしてみてください。
着床出血と生理の違いは?
生理の開始予定日とほぼ同じくらい、もしくは少し早いくらいの時期に起こるので、出血を見たときに「生理が来たのかもしれない」と勘違いする方も少なくありません。着床出血と着床出血と生理痛の大きな違いとしては、通常、出血の量や色、持続期間などが異なります。
| 着床出血 | 生理 | |
| 色 | 血が混じったようなピンク、茶色、鮮血色 | 赤から暗赤色 |
| 量 | 少量 | 多量 |
| 腹痛の程度 | 軽い生理痛程度、お腹の奥がチクチクする感じ | 人によっては激しくお腹が痛むこともある |
以上のように違いはあるものの、人によっては生理と区別がつかないような真っ赤な経血があり「いつも通りの生理がきた」と思ったら、それは着床出血で実は妊娠していた、ということもあります。
着床出血が続く期間
着床出血の場合の出血は大体の目安にはなりますが、着床出血は1〜2日程度と短く、長くても4日ほどで出血が止まります。「少し出血したと思ったらすぐに止まった」という人もいれば、「3日間くらい少量の出血が続いた」という人もいるので、かなり個人差があるといえます。
着床痛
医学的に証明されているものではありませんが、着床時期に感じる痛みを着床痛と呼ぶことがあります。また、痛みの感じ方は人それぞれです。生理痛とは少し違う「チクチクピリピリ」「ズキン」とした腹痛や腰痛を感じる方が多いですが、生理痛と同じような鈍痛である場合もあります。その他、胃痛や恥骨の痛み、さらにお腹や胸の張りや違和感などを感じることもあります。
たちくらみやめまい
妊娠初期には、立ちくらみやめまいなどを起こすことがあります。これらの症状は、ホルモンバランスの乱れがや血液の増加による赤血球の割合の減少が影響しています。血は潜在的な症状であることが多いため、普段よりも息切れがしやすい、顔色が悪いなどの体調の変化がある場合は無理をしないようにしましょう。ふらつきがでたときは、無理に立っていると頭から倒れたり、頭を打つなど怪我の原因にも繋がってしまいます。まずは落ち着いて、座るか横になるようにしましょう。
風邪に似た症状
妊娠が成立すると、女性ホルモンである黄体ホルモンの量が多くなります。プロゲステロンが増えると、眠気やだるさを引き起こすこともあるといわれています。着床後になんとなく風邪っぽい、微熱が出る、だるい、寒気があるといった症状を感じるのはこのためであると考えられています。
また、妊娠を希望する場合は基礎体温を計測することをおすすめします。低温期が続いたあと、いったん体温が下がり、その後急激に体温が上昇している時期があれば、そのときに排卵があったと推測できます。基礎体温を計測することで、自分の生理サイクルが分かるようになり、月経初日から何日後に排卵が起こるか予測できるようになるでしょう。
精神的な症状
着床時に見られる可能性のある症状の一つに、情緒不安定があります。着床、すなわち妊娠が成立すると、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンが増加します。これらのホルモンの影響で、人によっては、イライラしたり、わけもなく憂うつになったりといった精神的な症状が出やすくなります。
ただし、妊娠していなくても生理前は精神的に不安定になりやすいので、妊娠初期症状なのかどうか見分けにくいのも事実です。他の妊娠初期症状が現れていないか、あわせてチェックしてみましょう。
着床出血がみられたら妊娠検査薬で確認できる?
基本的に着床出血も通常の生理でも色や量、時期で見分けることは不可能に近いです。
着床出血が起きるのは性行為から2週間前後に起きるので元の生理周期が近い人であれば区別がつきづらいのです。
そのため、不安な性行為がある場合で着床出血かな?と思ったら妊娠検査薬を使用することをおすすめします。
通常の妊娠検査薬は生理予定日の1週間後から使用することができますが、早く結果を知りたいという方は生理予定日当日から使えるフライング妊娠検査薬を使ってみるのもよいでしょう。ただし、フライング検査薬は正確な結果が出にくいので、慌てずに生理予定日から1週間は待ってみてください。
妊娠検査薬はドラッグストアや薬局に売っており、使い方は簡単で検査薬に尿をかけることで結果が出る仕組みです。製品によって尿をかける時間は異なりますので説明書は必ず読んだ上で使用してください。尿をかけた後は判定が出るのを待ちます。ここで検査薬を水平な場所に置くことが大事なポイントです。判定結果は一般的に「判定窓に線がでたら陽性=妊娠の可能性がある」と捉えてよいでしょう。一方で判定窓に線がでなければ陰性といえます。
ただし妊娠検査薬の結果は100%といえるわけではないので、不安な性行為があった際には産婦人科を受診して検査することをおすすめします。
体外受精とは?妊娠するまでの流れ
体外受精とは不妊治療のひとつで、排卵直前に体内から取り出した卵子を体外で精子と受精させ、できた受精卵(胚)を子宮内に戻す治療のことです。
「体外受精は何回も受ける必要があるの?」と疑問を持つ人は少なくありません。大まかなスケジュールとして、体外受精をすると決めてから妊娠に至るまで、約1~2か月かかります。しかし、1回目の採卵と胚移植で妊娠できなかった場合には、さらに期間が延びることがあります。体外受精の流れは、排卵誘発、採卵、採精、受精、胚培養、胚移植といった流れになります。
最初のステップは、排卵誘発となりますが、通院が必要です。生理開始3〜10日頃に排卵誘発剤を使用します。
次のステップは採卵と採精です。こちらも通院が必要となります。生理開始11〜14日頃に卵子を採取します。採卵当日は、朝8時〜10時頃に行われ、所要時間は数分から数十分程度です。採卵日当日には、精子の採取も行います。
体外受精(受精、培養、分裂)は、採卵日当日に行います。受精してできた受精卵は細胞分裂を起こし、「胚」になります。胚はさらに細胞分裂して育っていきます。体外受精を行った後、インキュベーター内で2〜6日間、培養を行います。卵巣刺激法の種類、ホルモン値、子宮内膜の厚さなどを診断したのち、採卵した周期に胚移植が行われます。
胚移植は、育てた胚を、胚移植用のカテーテルを子宮腔内に進めて、胚を子宮に移植します。胚移植には、採卵した周期の新鮮胚(分割期胚または胚盤胞)を使用する場合と、凍結融解した胚(分割期胚または胚盤胞)を使用する場合があります。胚移植後の約2週間後に、血液検査あるいは尿検査のどちらかで妊娠判定を行います。妊娠により増えるhCGホルモンを測ることで、妊娠しているかが確認できます。
以上のようなスケジュールで体外受精は進められていきますが、要する期間や体外受精の成功状況には医療機関で異なり、個人差があるといえます。また、体外受精にはパートナーの協力も必要となるため、相談しながら治療を行うことが大切であるといえます。
通常の着床と体外受精による着床の違い
体外受精だからといって、通常の着床時と違いがあることはありません。症状に関しても、自然妊娠の時と同様に無症状の場合もあれば、着床出血や着床痛が起こることもあります。
体外受精の場合の、着床までの過ごし方
体外受精の移植後は「しっかり着床できているか」「受精卵が流れ出てしまうのではないか」など心配する人も多いでしょう。しかし、よほど激しすぎる運動などをしない限りは普通に生活していても妊娠率に影響をする問題はありません。移植後は、不安な気持ちが出てきたり、ストレスの多い時期ではありますが、普段通りの生活を心がけ、リラックスして過ごすように心がけていきましょう。
着床出血かもしれないと感じたら
出血が着床によるものの場合は、お腹の中で胎盤ができはじめ、赤ちゃんがお母さんから酸素をもらい始める時期となります。
赤ちゃんが無事に育つように見直すべき生活習慣があります。たばことアルコールは胎児の発育に悪影響を与えるため、妊娠を希望するタイミングでやめることが望ましいです。またカフェインの過剰摂取は避けるようにしましょう。1日1~2杯程度にとどめるか、カフェインレスの飲み物を用意しておくと良いでしょう。着床出血があり妊娠の可能性がある場合は、規則正しい生活を意識して過ごせるよう意識してみてくださいね。
着床出血以外の出血
着床出血と生理以外でも出血が起こることがあり、これを「不正出血」と呼びます。たとえば妊娠初期であれば、着床出血以外に子宮外妊娠や前置胎盤、切迫流産などの症状で出血することがあります。また妊娠していない場合も、排卵期出血、子宮頸管ポリープ、子宮がんなどの症状として出血が現れることもあります。
出血があった場合は落ち着いて出血の状態をチェックし、記録しておいて医師に相談しましょう。特に妊娠している場合はかかりつけ医に連絡し、指示を仰いでください。以下では、不正出血の症状が起きた場合に考えられる病気について解説していきます。
子宮外妊娠
子宮外妊娠の症状の1つに出血があります。子宮外妊娠とは、本来なら子宮内膜に着床するはずの受精卵が、子宮内膜以外で着床することをいいます。正式には「異所性妊娠」とも呼び、全妊娠の1〜2%の割合で発生する確率があります。超音波検査(経膣超音波検査)で子宮以外の場所に胎児が確認できた場合、子宮外妊娠となります。大変残念ですが妊婦の身体にも危険があるため、妊娠の継続はできません。
胞状奇胎
胞状奇胎とは何らかの原因で受精がうまくいかず、胎盤を作る組織の絨毛が、つぶつぶのように変化する疾患です。ぶどうの粒のように増殖することから、「ぶどう子」と呼ばれていたこともあるようです。頻度は全妊娠の500-1000回に1回程度といわれています。こちらも残念ながら妊娠の継続はできません。症状として性器出血や腹痛があり、週数が進んだ場合は高血圧、浮腫、蛋白尿などの症状がある場合もあります。
絨毛膜下血腫
絨毛膜下血腫とは、子宮内膜と絨毛膜(子宮の隣にある、外側の胎児膜)の間や、胎盤自体の下に血液が溜まることで、妊婦の4~22 %程度に見られると報告されています。絨毛膜下血腫の症状には性器出血と子宮収縮があり、超音波検査で絨毛膜下血腫の大きさを確認します。多くの場合が安静を保つことで妊娠中期頃には自然に吸収されて改善することが多いです。
子宮内膜症
子宮内膜症とは、本来なら子宮の内側の壁を覆っている子宮内膜が、子宮の内腔以外の部位(卵巣や腹膜、子宮の壁の中など)に発生し、発育を続ける疾患です。20~30代の若い世代の女性に発症することが多いとされています。女性の約10%程度が子宮内膜症というデータもあります。出血以外にも、月経痛や下腹部痛、腰痛や、排便痛、性交痛などの症状があります。年齢や妊娠希望に合わせて、薬物療法や手術などを選択します。低用量ピルを服用して、出血量や生理痛を軽くするという治療もあります。内膜症の予防という意味でも低用量ピルは有効なので、月経が重く悩んでいるという方は、ピルを選択肢にいれてもよいでしょう。
参照:子宮内膜症|公益社団法人 日本産科婦人科学会 (jsog.or.jp)
子宮筋腫
子宮筋腫とは、子宮の筋肉組織由来の良性腫瘍で、若い方から閉経後の方まで高頻度に見られる疾患です。症状の程度はそれぞれで、不正出血や腰痛、月経過多や月経痛などがあります。子宮筋腫は不妊や早産の原因にもなります。内診や超音波検査、MRI検査などで診断します。経血の量や生理痛の強さに違和感を感じた場合は医師に相談しましょう。
子宮頸がん・子宮体がん
子宮頸がんや子宮体がんなどの悪性腫瘍にも、不正出血の症状が見られる場合があります。その他排尿時痛や性交時痛、下腹部の痛みなどの症状がある場合もありますが、無症状の場合もあり、症状には個人差があります。子宮頸がんや子宮体がんの初期症状として最も多い自覚症は不正出血です。 出血の程度は、おりものに血が混ざり、褐色になるだけのものもあります。 他には、排尿時の痛みや排尿のしにくさ、性交時の痛み、下腹部の痛みなどの症状があり、進行した場合は腹部膨満感(おなかが張る感じ)があらわれることもあります。子宮頸がんは特に20代での進行が早いといわれています。1年に1回の子宮頸がん検診をお勧めします。
出血した時の対処方法
妊娠の可能性が示唆されている状態で、出血があった場合、特に避妊を希望している方は不安な気持ちでいっぱいになり、どう対処して良いかわからない方も多いのではないでしょうか。
そういった場合の対処法を紹介していきます。
妊娠検査薬を使う
先ほども紹介しましたが、着床出血があった際に一番手軽な方法として「妊娠検査薬」を使うことも、ひとつの手段です。
しっかり説明書を読み、タイミングと使用方法を守って使いましょう。
その上で、陽性の結果が出た場合は必ず産婦人科の受診をしてください。
陰性が出た場合は生理の可能性が高いですが、100%の正確性はないので、基本的には産婦人科を受診して検査するのをおすすめします。
産婦人科を受診する
妊娠検査薬ではあくまで素人判断になってしまうため、誤った結果が出た場合に妊娠を見逃してしまう場合があります。
出血量が少なかった場合でも産婦人科を受診することが無難といえます。
出血量以外でも、自分ではわからないところで緊急性を要する病態が進行している可能性があるため、妊娠が疑われる場合には産婦人科を受診するようにしましょう。
もし、受診するかどうか迷ってしまう場合は近くの産婦人科に電話をして病院の判断を仰ぎましょう。
着床出血と生理の違いについてよくある質問
一見見分けのつきづらい着床出血と生理の違いについて、よくある質問に答えていきます。
着床出血はいつごろ来る?性行為から何日後?
着床出血が起きるのは性行為から、おおよそ14日前後といわれています。
ただし排卵日の前後など性行為日にもよって変わってくるので、早い方では1週間、長くても2週間前後です。
14日間を嚙み砕くと排卵日に性行為があった場合、受精までは72時間、着床までは5日~6日間、着床完了までは12日間かかります。※1 つまり、着床出血が起きるのは着床開始から着床完了までの間が目安となります。ですので、おおよそ14日間前後(2週間)となります。
※1 期間はおおよそです。個人差があります。
着床出血の量はどれくらい?生理くらいの出血があったら?
着床出血における出血量は生理並みの出血量がでる確率は低いと言えますが、完全にないとは言い切れません。
ひとつ生理と違うところは、生理のように日が経つにつれて出血量が増えていくことはありません。
ほとんどの場合は1日、2日で終わるのが着床出血の特徴です。
着床出血が出てたから妊娠検査薬を使ったけど陰性だった、妊娠してない?
妊娠検査薬は製品によって検査可能なタイミングが異なりますが、一般的な妊娠検査薬は生理予定日から1週間後から使用できるものが多いです。
それより早くに妊娠検査薬を使用した場合は正しい結果が出ない場合があります。
仮に陰性が出たとしても妊娠している場合があるので、陰性が出ていても生理が来ない際は産婦人科を受診しましょう。
生理予定日を過ぎてから出血したら着床出血?
生理予定日を過ぎてからでも着床出血が出る場合もあります。
着床出血はすぐに排出されると色がピンク色や鮮血色で出てくることが多いです。
ですが反対に、時間が経ってから排出された場合は茶色のおりものとして出てくる場合もあります。
妊娠検査薬の結果が陽性であったり、出血量が多い場合には”子宮外妊娠”の場合があるので、そういった際には早急に産婦人科を受診してください。
着床出血でも生理でもない出血の可能性はある?
あります。
着床出血でも生理でもない出血を「不正出血」と呼びます。
ただし、妊娠をしている可能性があるのであれば、切迫流産が原因で出血している可能性があります。妊娠していないのであれば、子宮筋腫、頸管ポリープ、膣部びらん、子宮頸がんによって出血している可能性があります。
関連:新型出生前診断NIPTの最新情報とアドバイス | Nコラム(Ncolumn)
メデリピルなら安心してピルを始められる
「ピルを服用すると将来不妊になる?」と不安に思う方もいるかと思います。ピルの服用を止めると3ヶ月以内にほぼ90%の方で排卵が再開した症例もあります。しばらくすると自然な周期に回復し、排卵が起こるようになりますので安心してくださいね。
ピルの服用経験がなく、ピルを飲んでみたいけど、安心して信頼できる方法で始めたいという方に、オンラインピル診療・処方サービスのメデリピルがおすすめです。
メデリピルでは、現役の産婦人科医が診療から処方までをオンライン上で行い、自宅にピルが届くので、オンラインでも安心してピルを始めることができます。
メデリピルでは、ご自身に合ったピルを医師と相談しながら決めることができ、サービス利用期間中であれば診療代はずっと無料なので、服用中の不安なことや悩みを、いつでも医師に相談することができるサポート体制が整っています。
また、低用量ピル定期便 ※1 の場合、初月ピル代0円 ※2 で始めることができます。まずは試してみたい!という方におすすめです。
※1 3シート目受け取りまで解約不可
※2 別途送料550円

メデリピルは、いつでもスマホから簡単に受診できる、「誠実」と「続けやすい」を大事にしたオンラインピル診療サービスです。初月ピル代無料、診療代はずっと無料。国内最安クラスで提供しています。
※医師の診療時に処方された場合、最低3シートは服用いただいた上でご自身に合っているか判断していただきたいため、3シート目受け取りまでは解約は不可となります
メデリピルについて詳しく知る
→低用量ピルの料金について詳しくはこちら
メデリピルの5つのこだわり

1ヶ月無料のお試し期間
ピル初心者の方でも安心して服用いただけるよう、低用量ピルは初月無料でお届けします。
※医師の診療時に処方された場合、最低3シートは服用いただいた上でご自身に合っているか判断していただきたいため、3シート目受け取りまでは解約は不可となります
診療担当するのは現役の産婦人科医
専門的な知識を持った現役産婦人科医が診療を担当をするので、生理やカラダに関する不安や疑問を安心して相談することができます。
何度でも診療・再診無料
服用中の体調や副作用など、産婦人科の専門医にいつでも気軽にご相談ください。
予約から診療までLINEで簡単
診療予約や、予約日・配送日やプラン変更など、LINE一つで行うことができます。
正しい知識をお届け
ピルや女性のカラダに関する知識を定期的にお届けしています。
※メデリピルは医療機関とユーザーを繋ぐプラットフォームです
※診療やピルの処方等は保険適用外・自由診療であり、医療機関に所属する医師が行います
まとめ
今回の記事では、着床出血についてだけではなく、体外受精の着床についても解説していきました。着床出血は生理予定日の前に起きる少量出血です。妊娠を希望している時の出血は、不安になると思います。しかし、着床出血は胎盤を形成するための過程であり、異常な出血ではありません。「着床時出血かも」と思ったら、5日後に妊娠検査薬でチェックしてみましょう。一方で、妊娠を希望しない場合は低用量ピルの継続的な服用がおすすめです。妊娠を希望するまで飲み続け、妊娠を考え始めた時点でピルをやめて効率的に妊娠を目指す使い方もあります。
着床出血・生理の出血・不正出血など膣からの出血はどのような場合でも心配ですよね。それぞれ特徴があるものの、自分で見分けることが難しいこともあります。そのような場合は1人で抱えず医師に相談してみるといいかもしれませんね。
監修者

カテゴリ一覧
 漫画
漫画
こんな経験”あるある!”と思わず頷いてしまう?mederiユーザーからの体験談に基づいた、mederiオリジナル漫画シリーズです。生理やピル・女性の健康に関して、楽しく学んでみましょう!










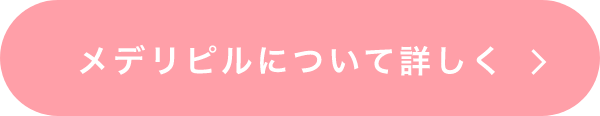

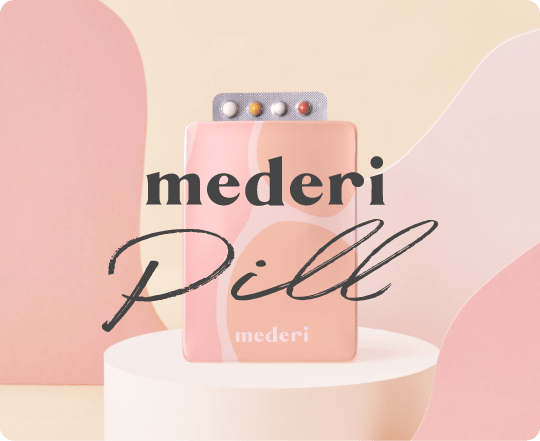







 予約に進む
予約に進む

