生理は女性にとって健康状態のバロメーターでもあります。
生理の基礎知識や、生理中でも快適に過ごすためのセルフケアをご紹介。
女性ホルモンの働きとは?卵胞ホルモンと黄体ホルモンの違いについても解説

女性は1ヶ月に4つの顔を持つ。なんて聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。女性のこころの変化を「女心と秋の空」と表す言葉が存在するほど、女性は心や体の状態が変動しやすいのです。このような変化は、女性ホルモンの働きが大きく影響しています。
今回は、女性ホルモンの働きや生理との関係性についてご紹介します。正しい知識を身につけて、ぜひ日々の生活に役立ててください。
もくじ
女性ホルモンとは
女性ホルモンは、主に卵巣でつくられる、身体を女性らしく保つために大切な物質です。女性ホルモンには「卵胞ホルモン(エストロゲン)」と「黄体ホルモン(プロゲステロン)」の2種類があります。それぞれの働きや違いについて解説していきます。
そもそもホルモンとは
ホルモンは、体の様々な生命機能を維持するために存在する大切な物質のひとつです。ホルモンにいくつか種類があることは広く知られていますが、体の中には100種類以上のホルモンやホルモンに似た物質が見つかっているのです。これらは今後の研究でさらに発見されていくといわれています。
「ホルモンバランスが大切」とはよく言われますが、ホルモンは多すぎても少なすぎても健康に影響があるのです。血液の中にほんの微量しか含まれていないホルモンですが、とても繊細な物質ということが分かります。
女性ホルモンの働き
女性ホルモンは、生理や妊娠・出産をするためだけに働いているのではありません。女性らしいボディラインを形成したり、ハリのある肌を保ったりと様々な働きをしています。生理前になると女性ホルモンの働きによって体調不良を起こす事もありますが、生殖機能を維持していくためには必要なプロセスの一つであることも覚えておきましょう。
女性ホルモンと生理の関係性
生理がある女性の心身の状態は約1ヶ月を1つの周期として繰り返しています。この周期をつくりだしているのが「卵胞ホルモン(エストロゲン)」と「黄体ホルモン(プロゲステロン)」という2種類の女性ホルモンです。この2つのホルモンは卵巣から分泌されていますが、そもそも分泌するためには脳下垂体から出る卵胞刺激ホルモンや黄体化ホルモンが関わっています。このように様々なホルモンが結びついて生理周期を繰り返しているのです。
また、正常な生理周期は25〜38日間、生理の期間は3~7日程度といわれています。ホルモンが正常に働いているかどうか、目に見える変化としてはわかりづらいですが、基礎体温を測っておくとサイクルを把握することができるでしょう。
卵胞ホルモンと黄体ホルモンの違い
ここでは女性の生殖機能に関わるホルモンとして代表的な卵胞ホルモンと黄体ホルモンについて、その役割や違いについて解説していきます。
卵胞ホルモン(エストロゲン)の役割
卵胞ホルモンは女性らしさをつくるホルモンで、成長とともに分泌量が増え、生殖機能を発育・維持させる働きをもっています。前述のように、女性らしい丸みのある体形をつくったり、コラーゲンの生成を促したりして、肌をみずみずしく美しく保つ働きもあります。
卵胞ホルモンの分泌量は20代後半で最も多くなります。その後、40歳前後から少しずつ分泌量が減少していきます。45歳を過ぎたころからこの分泌量は急激に低下し、50歳あたりになると閉経を迎えます。
黄体ホルモン(プロゲステロン)の役割
黄体ホルモンは妊娠維持のためのホルモンとして重要な役割をになっています。排卵直後から分泌量が増え、受精卵が着床しやすいよう、子宮内膜を厚く保ちます。妊娠すれば子宮内膜を維持するよう働きかけます。妊娠が成立しなければ、黄体ホルモンの分泌量は急激に低下し、それによって子宮内膜が剥がれ落ちて生理が起こります。
このホルモンの急激な低下によって、PMS(月経前症候群)が発生しているともいわれています。
生理の仕組み
女性の体は約1か月の期間のなかで、妊娠に備えて卵胞を育て、受精卵を着床させるための子宮内膜を準備していきます。しかし、妊娠が成立しなかった場合は準備した子宮内膜が不必要になるので、体から排出されていきます。これが生理となります。
この一連の流れは4つの期間に分類され、説明されます。それぞれ体の中でどのような動きがあるのかみていきましょう。
| 生理 | 妊娠が成立しなかった場合、子宮内膜が剥がれ落ち、体外に排出される |
| 卵胞期 | 卵巣で卵胞を育てる期間。エストロゲンの分泌が増加し、その影響で子宮内膜が厚くなる。 |
| 排卵期 | 成熟した卵胞から卵子が排出され、排卵が起こる。 |
| 黄体期 | 排卵後の卵胞が黄体に変化し、プロゲステロンを分泌。子宮内膜を厚く保ち、受精卵が着床しやすい環境に整える。 |
黄体期(黄体ホルモン)とうまく付き合うには
卵胞ホルモンには、女性らしさを保つことや美肌をキープするなど、良いイメージを持っていることが多い一方で、黄体ホルモンに対しては生理前や妊娠中の不調を起こすことから、良い印象を持っている方は少ないのではないでしょうか。
日常生活での健康管理がポイント
黄体ホルモンによる不調を過剰にしないためには、日々の健康管理が大切です。ここでは基本的な生活習慣の中で心がけたいポイントをお伝えしていきます。
・睡眠を取る
一見無関係に思えますが、睡眠不足は女性ホルモンの分泌に影響を及ぼすのです。睡眠不足になると自律神経が乱れ、その結果ホルモンバランスが乱れてしまいます。睡眠時間を確保するのはもちろんですが、質の高い睡眠が取れるよう、意識してみるのも効果的ではないでしょうか。
・バランスのとれた食事をする
バランスの良い食事は基本中の基本です。栄養素が偏ることなく摂取することはできていますか?忙しい女性にとっては手軽に済ませられるコンビニ食などは重宝しますが、足りない栄養素を補えるようなメニューにしてみましょう。
・運動習慣をつける
定期的な運動は運動不足解消だけでなく、心のリフレッシュにもなり一石二鳥です。運動習慣を付けることで血行が良くなり、生理前の厄介なむくみなども緩和できるかもしれません。
生理が辛い場合には、専門医に相談を
生理前の不調が辛かったり、生理痛が重かったりと、生理にまつわるトラブルは人それぞれです。そんな時こそ、低用量ピルの服用を検討してみてはいかがでしょうか。低用量ピルと聞くと純粋に「避妊」のイメージがありますが、その副効用から多くの方が生活改善薬として服用を始めています。低用量ピルは、少量の女性ホルモンが含まれているため、ホルモンの急激な増加や低下を緩和し、安定したホルモンバランスで過ごすことができるのです。
ピルをはじめるならメデリピル
低用量ピルを服用することでホルモンバランスをコントロールすることができます。
ピルの服用経験がなく、ピルを飲んでみたいけど、安心して信頼できる方法で始めたいという方に、オンラインピル診療・処方サービスのメデリピルがおすすめです。
メデリピルでは、現役の産婦人科医が診療から処方までをオンライン上で行い、自宅にピルが届くので、オンラインでも安心してピルを始めることができます。
メデリピルでは、ご自身に合ったピルを医師と相談しながら決めることができ、サービス利用期間中であれば診療代はずっと無料なので、服用中の不安なことや悩みを、いつでも医師に相談することができるサポート体制が整っています。
また、低用量ピル定期便 ※1 の場合、初月ピル代0円 ※2 で始めることができます。まずは試してみたい!という方におすすめです。
※1 3シート目受け取りまで解約不可
※2 別途送料550円

メデリピルは、いつでもスマホから簡単に受診できる、「誠実」と「続けやすい」を大事にしたオンラインピル診療サービスです。初月ピル代無料、診療代はずっと無料。国内最安クラスで提供しています。
※医師の診療時に処方された場合、最低3シートは服用いただいた上でご自身に合っているか判断していただきたいため、3シート目受け取りまでは解約は不可となります
メデリピルについて詳しく知る
→低用量ピルの料金について詳しくはこちら
メデリピルの5つのこだわり

1ヶ月無料のお試し期間
ピル初心者の方でも安心して服用いただけるよう、低用量ピルは初月無料でお届けします。
※医師の診療時に処方された場合、最低3シートは服用いただいた上でご自身に合っているか判断していただきたいため、3シート目受け取りまでは解約は不可となります
診療担当するのは現役の産婦人科医
専門的な知識を持った現役産婦人科医が診療を担当をするので、生理やカラダに関する不安や疑問を安心して相談することができます。
何度でも診療・再診無料
服用中の体調や副作用など、産婦人科の専門医にいつでも気軽にご相談ください。
予約から診療までLINEで簡単
診療予約や、予約日・配送日やプラン変更など、LINE一つで行うことができます。
正しい知識をお届け
ピルや女性のカラダに関する知識を定期的にお届けしています。
※メデリピルは医療機関とユーザーを繋ぐプラットフォームです
※診療やピルの処方等は保険適用外・自由診療であり、医療機関に所属する医師が行います
まとめ
女性ホルモンは健康維持のために役立っている反面、体調不良などでうんざりしてしまうこともありますよね。自分の体を大切に愛でていくためにも、女性ホルモンや生理の仕組みを理解し、うまく付き合っていくことが大切です。日常生活での健康管理のポイントもお伝えしましたが、生理トラブルに悩んでいる方は低用量ピルの服用を選択肢の一つとして検討しても良いでしょう。
監修者

カテゴリ一覧
 漫画
漫画
こんな経験”あるある!”と思わず頷いてしまう?mederiユーザーからの体験談に基づいた、mederiオリジナル漫画シリーズです。生理やピル・女性の健康に関して、楽しく学んでみましょう!







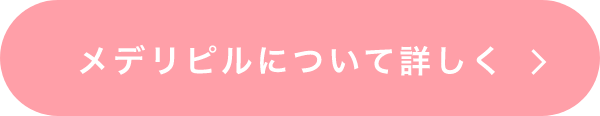

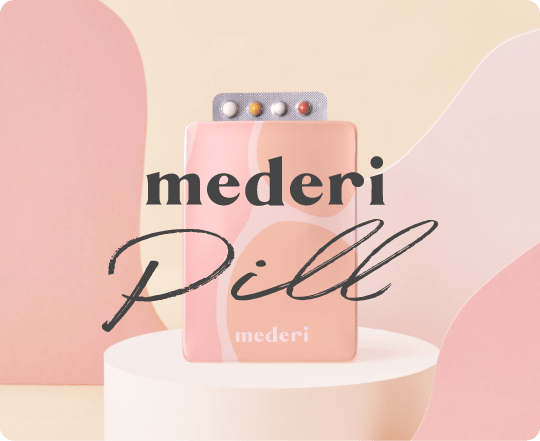







 予約に進む
予約に進む

